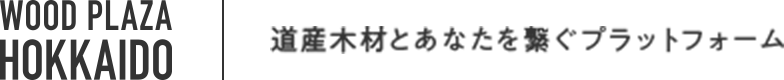人を育て、森を育てる学び舎。
北の森づくり専門学院は、道内初の林業の専修学校として、令和年4月に開校しました。
新校舎では、学生80名が講義・実習を通して、最新の林業・木材産業の知識や技術を学びます。
道産木材がふんだんに使用された室内は、木の香りが漂い、明るく、温かみのある空間です。
晴れた日には、ホールから大雪山系の山並みが一望でき、雄大な旭川の自然を感じることもできます。
設計・施工の特徴
敷地は旭川市西神楽の国道237号線に面する北海道林産試験場内の庁舎棟西側に隣接した平坦な空き地です。
建築は庁舎棟と国道側の外壁面を揃えた木造2階建(一部鉄筋コンクリート造)で、国道側にエントランスホールとエネルギー棟を配置しています。

プランは、1階に職員室・実習室、2階に基礎教室をそれぞれ南側に配置し、静かで明るい居室環境を実現しました。
北側エントランスホールは吹抜空間となり、2階のホールに階段で連続し、上部南面にハイサイドライトを設ける事で四季の太陽高度により、変化のある光の環境を実現しました。

主要構造部、仕上は全て道産木材を利用し、構造材にカラマツ・トドマツを使用し、外壁にはカラマツ、内部仕上げにスギ、ナラやシナを採用。構造フレームはカラマツ無垢材を加工したコアドライ材とトドマツ・カラマツのCLTを併用し ております。小径木であるコアドライ材による架構を計画し、小スパンによる柱材を真壁として列柱の表現とすることで、森の中のような木の林立するリズム・木の繊細さと美しさを感じるシンプルな計画としました。

エントランスホールの吹き抜けの大きなスパンも、小径木のコアドライで張弦梁架構を構築し、ハイサイドライトからの光で森の中の木漏れ日のような光がホール全体に降り注ぎます。
連続する全面木製 カーテンウォール(カラマツ)のガラスを通じて周辺環境に柔らかな木質の光の環境が伝わることを意図しました。
また、実習室・教室のY方向壁をCLTとし、10.80m×18.45mの無柱空間を実現するために、2階床にCLT板(6m×1.2m)をつなぎ、下部(実習室天井)を鋼製張弦梁で吊り上げる構造としております。

設備は林業の学校の設備としてふさわしい道産木質チップを熱源とした暖房システムを採用しています。
木質チップは間伐材や林地未利用材等から作られ、燃焼によって大気中の二酸化炭素濃度に影響を与えないカーボンニュートラルなエネルギー源です。道産木材をエネルギーとしても利用し、エネルギー棟内のバイオマスチップやチップボイラーを外部から見えるようにすることで、教育教材としても機能するよう計画しています。
ここで2年間校舎で過ごす学生が日々の生活を通して木材の持つ魅力と本質を体感し、林業につながる可能性を学び未来を拓くことを心より願っております。

Data
施設名/ 北海道立北の森づくり専門学院
所在地/ 旭川市西神楽1線10号
構造及び階数 / 木造一部RC 地上2階 地下1階
建築面積/ 1033.41㎡
延床面積/1289.72㎡
竣工年月日 / 令和3年1月
建築主/ 北海道
設計者/建築:(株)遠藤建築アトリエ 構造:(株)安藤耕作構造計画事務所 電機・設備:(株) ビーゴーイング
施工者/建築一工区:高組・多東・サンエービルド特定建設工事共同企業体 建築二工区:荒井・谷脇 経常建設共同企業体
[木材の使用量と施工状況]
構造材
・カラマツ集成材/柱、梁/64.2㎥
・カラマツコアドライ材/柱/19.5㎥
・トドマツ CLT/46.9㎥
・カラマツ CLT/110.9㎥
羽柄材
・トドマツ/78.7㎥
外装
・カラマツ/羽目板/5.0㎥
・カラマツ/45×45突付/16.3㎥
・カラマツ/ルーバー/1.4㎥
内装
・カラマツ/羽目板/0.2㎥
・エゾマツ/内部建具2箇所
・道南スギ/羽目板/264.3㎡
・カバ/複合フローリング/203.9㎡
・ナラ/複合フローリング/129.3㎡
道産材以外
・構造材 ヒノキ/土台/3.0㎥
[資材の調達方法]
道産材・道内加工を基本とし、CLT はオホーツクウッドピア、コアドライ材は栗山町ドライウッド(協)、 その他を厚浜木材加工(協)にて加工・組立を行いました。
[施設概要]
道内初の林業の専修学校として、令和年4月に開校。
学生が講義・実習を通して、最新の林業・木材産業の知識や技術を学ぶ。
Builder’s Voice
百年先を見据えた森林づくりを目指し、林業・木材産業における人材育成を行うための学校の計画です。
その為の建築計画で大切に考えたことは
・木造の新しい感性に響く空間を創る
・未来につながる木造の新しい技術の可能性を拓く
・木材に包まれ、木造の暖かさが伝わる外観を創る
・木材の構造や仕上げの質感に触れ木質の感性を育む
・エネルギーとしての木材がもたらす地球環境の未来を学ぶ
・光や風、周辺環境との関係を太陽・風土の持つ力として空間化することは、風土の中で森を創ることの本質と通じると考える
上記の視点を通して「森づくり」と「建築」の目指す世界がつながることを意図して計画を進めました。この学校を通じて、北海道の林業の可能性と発展を卒業生が拓き、循環型の豊かな北海道の森が形成され、美しい世界が創られることを願っております。
[株式会社遠藤建築アトリエ]