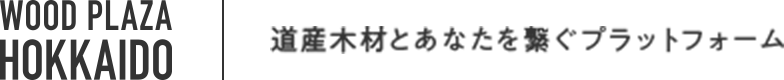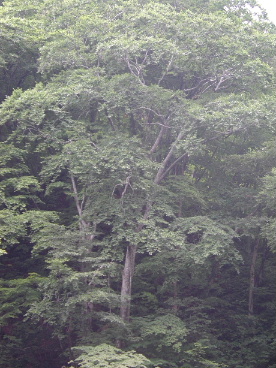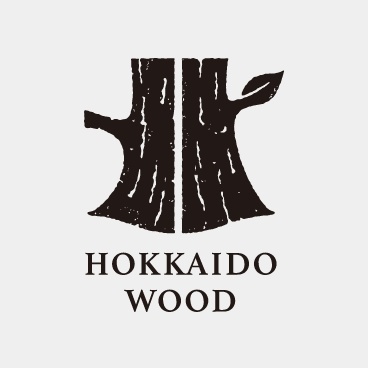お知らせ
都市木利用拡大宣言事業者の登録に係る要領を公開しました!
北海道の木材で、
心を豊かに。 Energizing the forest and
enrich your heart
心を豊かに。 Energizing the forest and
enrich your heart
SCROLL DOWN
INFORMATIONお知らせ
-
General一般の方は
こちら -
Vendor木材業者の方は
こちら
SEARCH BY PURPOSE目的別で探す
北海道の木材を使って
ほしい理由
北海道の木材を暮らしに取り入れることで、北海道の森林を元気にすることができます。
地域で生産された木材や木製品を地域で使うことで、林業や木材産業が活性化し、経済的な効果が生まれます。さらに、地域の森林に還元された資金で森林の手入れを行うことで、国土の保全に繋がり、遠くから木材を運ぶ際に発生するCO2の削減にも貢献します。
このように、私たちが積極的に地域で生産された木材を使うことで、森林と地域の活性化という良い循環が生まれます。
家具、食器、小物や雑貨など、身の回りの小さなものからでも
あなたの暮らしに北海道の木材を取り入れてみませんか?

Using wood
from Hokkaido
Reason for
wanting it
北海道樹木図鑑Hokkaido tree encyclopedia